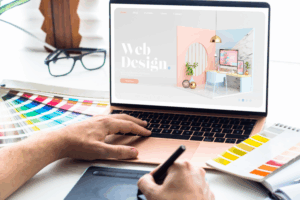業者に頼む前に!初心者でもできるバナーデザインの基本と自作のコツ
バナーデザインは自作できる?外注する前に知っておきたいポイント
どんな業種であれバナーデザインは集客や商品PRに欠かせない存在です。SNS投稿やWebサイトの告知、チラシ広告など、あらゆる場面で「視覚的に伝える力」が求められます。
しかし、毎回デザイン会社や外注に依頼すると、費用がかさむのが悩みどころ。「できれば自分で作れないだろうか?」と考える方も少なくありません。
実は、基本を押さえれば初心者でも十分にバナーを自作できます。まずは外注に出す前に、自作のメリットと基本を理解しておくことが大切です。
初心者でも押さえておきたいバナーデザインの基本3原則
レイアウトはシンプルに「伝える情報は1つ」
初心者がやりがちなのが「情報の詰め込みすぎ」です。キャンペーンの日時、店舗情報、サービスの特徴など、すべて盛り込みたくなる気持ちは分かりますが、伝える情報は1つに絞るのが鉄則です。
例えば「50%OFFセール開催中」というメッセージを中心に置き、補足は最小限にすることで、視覚的に分かりやすいデザインになります。
色とフォント選びで印象が決まる
バナーの印象は、配色とフォントで大きく変わります。コーポレートカラーやブランドカラーを軸にし、補色を効果的に使うと統一感が生まれます。
フォントも「ゴシック体で読みやすさを優先」「明朝体で高級感を演出」など目的に応じて使い分けることが重要です。
視線の流れを意識した配置
人の視線は左上から右下へと流れる傾向があります。キャッチコピーを左上に配置し、商品の写真や行動喚起(CTA)を右下に置くと、自然と伝えたい情報に目が行きやすくなります。
レイアウトに迷ったら「Z字」や「三分割法」を意識するのも効果的です。
バナーデザインを自作するときに使える無料・低コストツール
Canva:テンプレート豊富で初心者向け
「デザインが苦手でもすぐに形にしたい」という方におすすめなのがCanvaです。
豊富なテンプレートを選んで文字や色を調整するだけで、短時間で完成度の高いバナーが作れます。
とりあえず見た目をどうにかしたい!という方に最適なツールです。
Figma:共同編集やWeb制作との相性が良い
Webデザインやチームでの作業を想定するならFigmaが便利。
クラウド上で動くため、複数人で同時に編集が可能。拡張機能も豊富で、バナー制作だけでなくWebサイトのデザインにも発展的に活用できます。
近年では多くのデザイン会社で利用されています。
PowerPointやGoogleスライドでも代用可能
実は、ビジネスで馴染み深いPowerPointやGoogleスライドでもバナーは作成可能です。
シンプルな図形やテキストを組み合わせるだけで、SNS用のバナーや広告画像が作れるので、まずは身近なツールで練習するのも一つの方法です。
初心者が自作する際に注意すべきデザインのNG例
情報を詰め込みすぎて読みにくい
「せっかくだから全部載せたい」と思っても、情報量が多いと読者は混乱します。
伝えたいメッセージを一つに絞り、必要なら複数のバナーを作って分けることをおすすめします。
商用利用できない画像やフォントを使ってしまう
ネットで見つけた画像やフォントをそのまま使うと、著作権侵害につながる危険があります。
必ず商用利用可能な素材サイトや公式フォントを利用しましょう。UnsplashやPixabayなどのフリー素材サイトは便利です。(ちなみに筆者は写真ACをよく利用しています)
サイズや解像度を確認せずに作ってしまう
SNSやWeb広告は媒体ごとに推奨サイズがあります。サイズを間違えると画像がぼやけたり、重要な部分が切り取られてしまうことも。
事前に規格を確認し、解像度も72dpi以上を意識して作成しましょう。
バナーデザインはどこまで自作できる?プロに依頼すべきケース
バナーは自作でも十分対応できますが、場合によってはプロに依頼した方が効率的です。
ブランド全体で統一感を出したい場合
複雑なデザインや高いクオリティが求められる場合
効果測定や改善までサポートしてほしい場合
プロに依頼することで、戦略的にデザインを組み立てられるだけでなく、自分の時間をコア業務に集中できます。自作と外注を状況に応じて使い分けるのが賢い選択です。
まとめ:まずは自作で挑戦、必要に応じて外注を検討
バナーデザインは「難しそう」と思われがちですが、基本を押さえれば初心者でも十分に自作できます。
ポイントは、シンプルなレイアウト、適切な色とフォント選び、そして媒体に合ったサイズ設定。
CanvaやFigmaといった便利なツールを活用すれば、デザイン経験がなくても短時間で高品質なデザインが可能です。
まずは自作で小さな一歩を踏み出し、必要に応じてプロに依頼する。この柔軟な姿勢こそ、効率的で成果につながるデザイン活用法です。